東海道中膝栗毛 三巻 7 十丁裏 十一丁表 十返舎一九 通油町(東都) : 栄邑堂, 享和2-文化11
東海道中膝栗毛 三巻
発端,初,後,3-8編 / 十返舎一九 著
十返舎一九 1765-1831
通油町(東都) : 栄邑堂, 享和2-文化11[1802-1814]序
18冊 ; 19cm
滑稽本
書名は発端の巻頭による その他の巻頭書名:浮世道中膝栗毛,東海道中膝栗毛 序題:膝栗毛 題簽書名:浪華見物滑稽膝栗毛 見返し題:東海道中滑稽記膝栗毛,洛中滑稽之記膝栗毛 扉題:中ッ腹五十三次売ッ尻道中之記
序:芍薬亭主人ほか
共同刊行:河内屋太助(大阪心斎橋唐物町)ほか
和装
印記:拾翠艸堂児戯之記
読んでいるのは、早稲田大学 ヘ13 03123 3巻目
十丁裏
斯(かく)て山中といへる建場(たてば)に似たる、爰ハ両側に、茶
屋軒をならべて、「おやすみなさいまァし、くだり
諸白(もろはく)もおざりやァす、もち(餅)よヲ、あがりやァし、いつ
せんめしヲあがりやァし、お休みなさいやァし/\
弥二「きた八、ちつと休んでいかふ、 ト ちゃ屋へ入る、此内のにハにつきたてたる、へつついのまへへ
おもてのかたより、たけのきせるをくはへて、一人のくもすけ、ずつと入り、「おへねへひやうたゝれどもだ、
ある熊や、どぶ八目が、峠まで長持ちでゆつたァな、
十一丁表
ひとりのくもすけ「ゑいは、そんざいあびてが、あんどんにげんこ(五十)ハ
ふんだくるべい、この長もちといふハ、六百の事、あびごといふハ、さりての事也、今一人「コレそりやァ
ゑいが、コノやろうが、しやらくを見ろべ、しつかりもん
つきをきァがつた、酒ごもきている雲すけ、「きんによう(昨日)、小田原
の甲州屋で、やらやつと壱まいもらつてきたが、あん
まり裾が長くて、お医者様のよふだとけつかる
丸はだかのくも、「やろうめらァ、工面がゑいから、すきなものをき
やがる、こんぢう(此中)内から、はだかでゐりやァ、がら
建場(たてば)
1 江戸時代、宿場と宿場の間の街道などで、人足、駕籠かきなどの休息した所。
明治以後は人力車や馬車などの発着所をいう。
2 人の多く集まる所。たまり場。
3 位置。たちば。
4 業者がその日に集めた廃品を買い取る問屋。
諸白(もろはく)
諸白(もろはく) とは日本酒の醸造において、麹米と掛け米(蒸米)の両方に精白米を用いる製法の名。
または、その製法で造られた透明度の高い酒、今日でいう清酒とほぼ等しい酒のこと。
一方、麹米は玄米のままで、掛け米(蒸米)だけに精白米を用いる製法、またはその製法で造られた酒のことを片白(かたはく)という。
麹米、掛け米ともに精白しなければ並酒(なみざけ)と呼ばれた。
諸白(もろはく)もおざりやァす、
→ 諸白(もろはく)もございます
げんこ(五十)
① 固く握った手。
② 〔近世、馬子、駕籠(かご)かきなどが用いた隠語〕 五・五〇・五〇〇などの金額。片手
甲州屋
実家の宿屋か、酒屋。(日本古典文学全集 頭注)
やらやつと
やっとの事で。(日本古典文学全集 頭注)
裾が長くて
医者の着る気長い合羽に見立てて(日本古典文学全集 頭注)




 ’
’
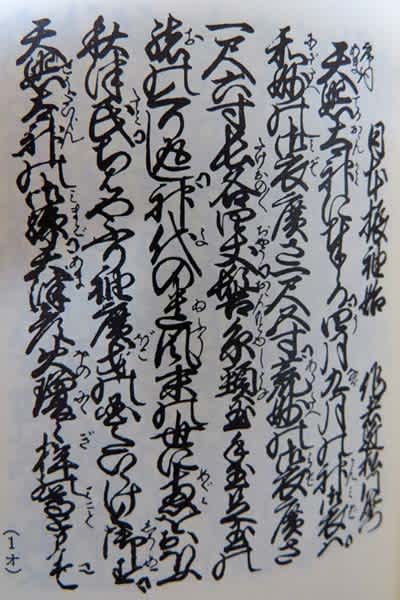
 が屏風絵を見て詠ったと云う、奈良竜田川の歌
ちはやぶる 神代も聞かず 竜田川 からくれなゐに 水くくるとは
戈
1 両刃の剣に長い柄をつけた大昔の武器。
「―をおさめる」(戦いをやめる)
2「鉾山車(ほこだし)」の略。ほこを立てて飾った山車(だし)。山鉾(やまぼこ)。
たいらけく
【文語】ク活用の形容詞「平らけし」の連用形。
平らけし(穏やかだ。 無事だ。)
御(しろしめ)す
1 領有なさる。統治なさる。▽「知(領・治)る(=治める)」の尊敬語。
出典古今集 仮名序「天皇(すべらぎ)の、天(あめ)の下しろしめすこと」
[訳] 天皇が天下を統治なさることが。
が屏風絵を見て詠ったと云う、奈良竜田川の歌
ちはやぶる 神代も聞かず 竜田川 からくれなゐに 水くくるとは
戈
1 両刃の剣に長い柄をつけた大昔の武器。
「―をおさめる」(戦いをやめる)
2「鉾山車(ほこだし)」の略。ほこを立てて飾った山車(だし)。山鉾(やまぼこ)。
たいらけく
【文語】ク活用の形容詞「平らけし」の連用形。
平らけし(穏やかだ。 無事だ。)
御(しろしめ)す
1 領有なさる。統治なさる。▽「知(領・治)る(=治める)」の尊敬語。
出典古今集 仮名序「天皇(すべらぎ)の、天(あめ)の下しろしめすこと」
[訳] 天皇が天下を統治なさることが。




